日本口腔インプラント学会は、会員数1万5,000人以上を有する歯科系最大の学会として成長しました。この間、インプラント治療に対する信頼を獲得し、現在は超高齢社会に向けての多職種連携による歯科治療、および口腔健康管理の責務を果たすべく、さまざまな取り組みを展開しています。そこで同学会理事長である宮崎隆先生に、学会のこれまでの歩みや現在の活動についてお伺いしました。
インプラント治療に対する国民の信頼回復に努める
本学会は1972年に設立された日本歯科インプラント学会と、日本デンタルインプラント研究学会をルーツとし、1986年に両学会が合併し、日本口腔インプラント学会として発足しました。2005年には社団法人となり、2010年に公益社団法人格を取得しました。また会員数は2009年から1万人を突破して急成長し、現在は会員数1万5,000人以上という、歯科系最大の学会となりました。
この間の道のりは決して平坦ではなく、我々にとって一番大きな試練は、2011年暮れの国民生活センターによる「歯科インプラント治療に係る問題-身体的トラブルを中心に-」の報道発表でした。その後、NHKでも取り上げられ、社会でインプラントに対するバッシングや批判が起こったことでした。
そのため、本学会では渡邉文彦前理事長時代の執行部の下で、国民の信頼を取り戻すためのさまざまな取り組みを行いました。例えば、国民向けに「口腔インプラント治療相談窓口」を全国に100カ所設置したほか、専門医制度のカリキュラムと試験方法を整備する、インプラント治療の指針をつくる、患者さんが所持するインプラントカードや、歯科医へのインプラント治療時のチェックリストなどを作成し、注意喚起を実践しました。
また本学会では、すでに一般社団法人日本老年歯科医学会と協働で高齢者施設におけるインプラントの実態調査を進めてきました。こうした調査結果を分析することで、世界に先駆けて高齢化が進んでいる我が国から、世界に向けたインプラント治療の情報発信をしていきます。
学会員へのサービス向上を目指し、歯科医がプライドを持てる学会に
今後の執行部の活動目標は、会員サービスの一層の向上です。「このサービスがあるから、この学会に入ってよかった」と思ってもらえ、会員であることにプライドを持てる学会にしたいと思っています。そのために、主に①学術講演会の開催、②機関誌の発行、③会員の認定制度、という3つの事業を展開しています。
まず、学術講演会については、例えばこの9月に開催される第48回学術大会の内容を見ていただければお分かりになるように、できるだけ多くの会員に参加したいと思われるような、魅力あるプログラムの企画を行います。そして、学術大会を通じて学会の立場を歯科界ならびに社会に「大阪宣言」として表明します。
機関誌としては現在、学会誌と国際誌(IJID)を発行しています。学会誌は、会員が臨床研究や症例報告を投稿しやすい環境整備を図り、総説論文や解説論文を掲載し、会員への有益な情報提供を行っています。国際誌はドイツインプラント学会と連携して、電子ジャーナルとして発行しており、国際誌として高い評価を受けています。
また、歯学でもこの4月に一般社団法人日本歯科専門医機構が発足し、本学会の認定制度については、専修医や専門医を申請しやすい環境整備を行います。さらに、試験の運営方法も改善し、できるだけ多くの会員がインプラント治療の専門資格を取得できるように支援していきたいと考えています。
本学会はすでに特定非営利活動法人日本歯周病学会と協働で、インプラントのメンテナンスに関する学会見解を公表しました。今後もインプラント治療や歯科治療に関わる共通課題に対して、他の専門学会と協働し、公益社団法人として社会への責任を果たしていきます。
学術団体として、口腔インプラント学の学問体系を確立し、研究を活性化させるとともに、学的根拠に基づいたインプラント治療にかかわるガイドライン・治療指針や教育プログラムを整備します。その上で、超高齢社会における我が国において、国民により良いインプラント治療が提供できるように、50年後、100年後を見据えた、口腔インプラント学の研究を進めていきます。
ニューヨーク(米国):ニューヨーク大学歯学部(NYU ...
フランス、パリ : 9月29日の朝、フランス ...
ライブウェビナー
月. 22 4月 2024
11:00 午後 JST (Tokyo)
Prof. Dr. Erdem Kilic, Prof. Dr. Kerem Kilic
ライブウェビナー
水. 24 4月 2024
2:00 午前 JST (Tokyo)
ライブウェビナー
水. 24 4月 2024
9:00 午後 JST (Tokyo)
Dr. Yin Ci Lee BDS (PIDC), MFDS RCS, DClinDent Prosthodontics, Dr. Ghida Lawand BDS, MSc, Dr. Oon Take Yeoh, Dr. Edward Chaoho Chien DDS, DScD
ライブウェビナー
木. 25 4月 2024
2:00 午前 JST (Tokyo)
ライブウェビナー
土. 27 4月 2024
1:00 午前 JST (Tokyo)
ライブウェビナー
火. 30 4月 2024
1:30 午前 JST (Tokyo)
Prof. Roland Frankenberger Univ.-Prof. Dr. med. dent.
ライブウェビナー
水. 1 5月 2024
2:00 午前 JST (Tokyo)



 オーストリア / Österreich
オーストリア / Österreich
 ボスニア・ヘルツェゴビナ / Босна и Херцеговина
ボスニア・ヘルツェゴビナ / Босна и Херцеговина
 ブルガリア / България
ブルガリア / България
 クロアチア / Hrvatska
クロアチア / Hrvatska
 チェコ共和国とスロバキア / Česká republika & Slovensko
チェコ共和国とスロバキア / Česká republika & Slovensko
 フランス / France
フランス / France
 ドイツ / Deutschland
ドイツ / Deutschland
 ギリシャ / ΕΛΛΑΔΑ
ギリシャ / ΕΛΛΑΔΑ
 イタリア / Italia
イタリア / Italia
 オランダ / Nederland
オランダ / Nederland
 ノルディック / Nordic
ノルディック / Nordic
 ポーランド / Polska
ポーランド / Polska
 ポルトガル / Portugal
ポルトガル / Portugal
 ルーマニアとモルドバ / România & Moldova
ルーマニアとモルドバ / România & Moldova
 スロベニア / Slovenija
スロベニア / Slovenija
 セルビア&モンテネグロ / Србија и Црна Гора
セルビア&モンテネグロ / Србија и Црна Гора
 スペイン / España
スペイン / España
 スイス / Schweiz
スイス / Schweiz
 七面鳥 / Türkiye
七面鳥 / Türkiye
 英国とアイルランド / UK & Ireland
英国とアイルランド / UK & Ireland
 国際的 / International
国際的 / International
 ブラジル / Brasil
ブラジル / Brasil
 カナダ / Canada
カナダ / Canada
 ラテンアメリカ / Latinoamérica
ラテンアメリカ / Latinoamérica
 米国 / USA
米国 / USA
 中国 / 中国
中国 / 中国
 インド / भारत गणराज्य
インド / भारत गणराज्य
 パキスタン / Pākistān
パキスタン / Pākistān
 ベトナム / Việt Nam
ベトナム / Việt Nam
 ASEAN / ASEAN
ASEAN / ASEAN
 イスラエル / מְדִינַת יִשְׂרָאֵל
イスラエル / מְדִינַת יִשְׂרָאֵל
 Algeria, Morocco & Tunisia / الجزائر والمغرب وتونس
Algeria, Morocco & Tunisia / الجزائر والمغرب وتونس
 中東 / Middle East
中東 / Middle East
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2023/09/ITI-World-Symposium-2024_-Singapore.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2022/08/MicrosoftTeams-image_new.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2022/08/exocad_DentalCAD_3_1_Rijeka_Press_Release_1920x1080_Splashscreen_01-2.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2022/05/MicrosoftTeams-image-27.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2021/08/1___Dr-Ginal-Bilimoria-780x439-.jpg)




:sharpen(level=0):output(format=png)/up/dt/2014/02/3shape.png)
:sharpen(level=0):output(format=png)/up/dt/2021/02/logo-gc-int.png)
:sharpen(level=0):output(format=png)/up/dt/2023/08/Neoss_Logo_new.png)
:sharpen(level=0):output(format=png)/up/dt/2010/11/Nobel-Biocare-Logo-2019.png)
:sharpen(level=0):output(format=png)/up/dt/2014/02/MIS.png)
:sharpen(level=0):output(format=png)/up/dt/2022/01/Sprintray_Logo_2506x700.png)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2018/09/p6_miyazaki_DSC4361.jpg)

:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2023/09/ITI-World-Symposium-2024_-Singapore.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=gif)/wp-content/themes/dt/images/no-user.gif)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2018/03/p3.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2018/06/p6_.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2018/06/p3_-e1529643581376.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2018/03/DSC9425.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2018/09/p7_0009.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2021/04/5___Prof.-Robert-Glickman-right-shows-Dr.-Huzefa-Talib-the-plan-that-will-guide-the-robot-in-placing-the-implant-into-the-patient%E2%80%99s-jawbone-1188x668-.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2017/12/%E8%88%B9%E8%B6%8A-%E6%A0%84%E6%AC%A1.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2018/06/p4_1.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2016/10/6c7c1d5af60a1caed08a74b28d74e3dd.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2017/01/8a06fe49fae0ea8ec9b90f7b5609546b.jpg)



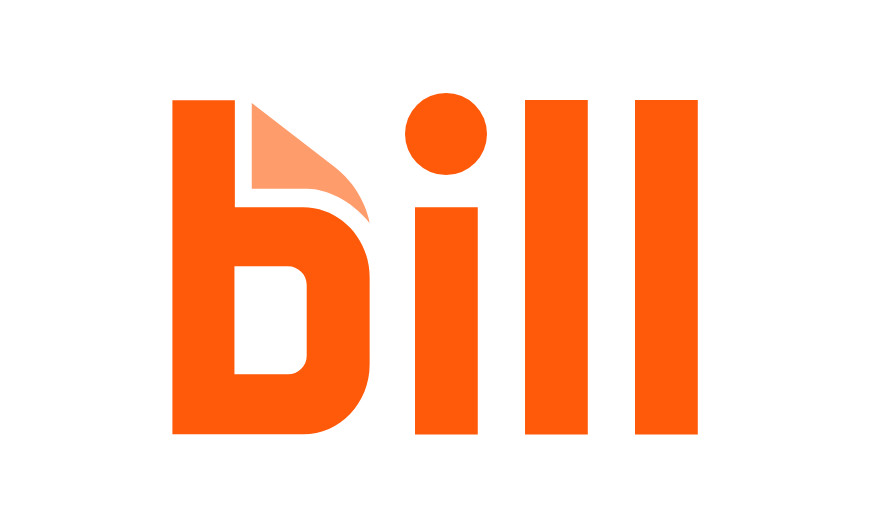

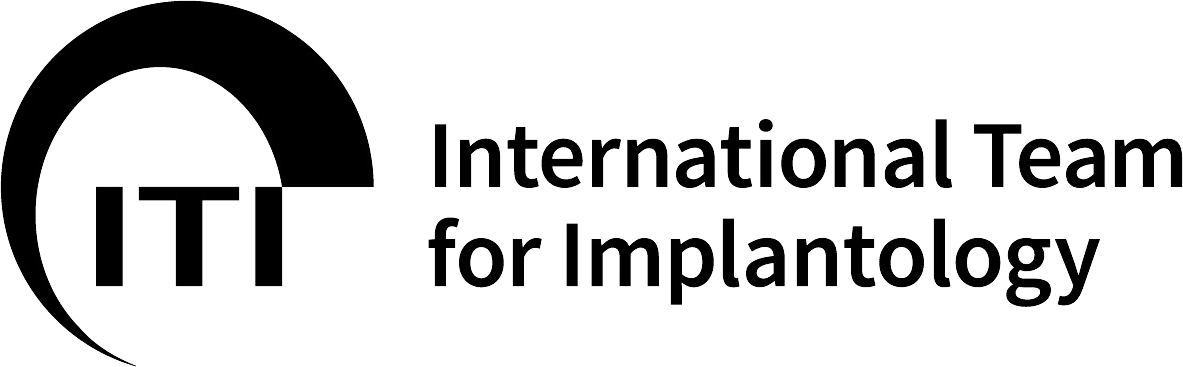




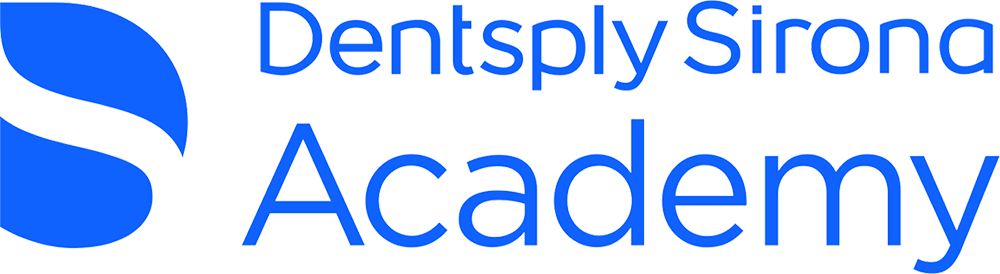






:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2023/09/ITI-World-Symposium-2024_-Singapore.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2022/08/MicrosoftTeams-image_new.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/up/dt/2022/08/exocad_DentalCAD_3_1_Rijeka_Press_Release_1920x1080_Splashscreen_01-2.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/wp-content/themes/dt/images/3dprinting-banner.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/wp-content/themes/dt/images/aligners-banner.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/wp-content/themes/dt/images/covid-banner.jpg)
:sharpen(level=0):output(format=jpeg)/wp-content/themes/dt/images/roots-banner-2024.jpg)
To post a reply please login or register